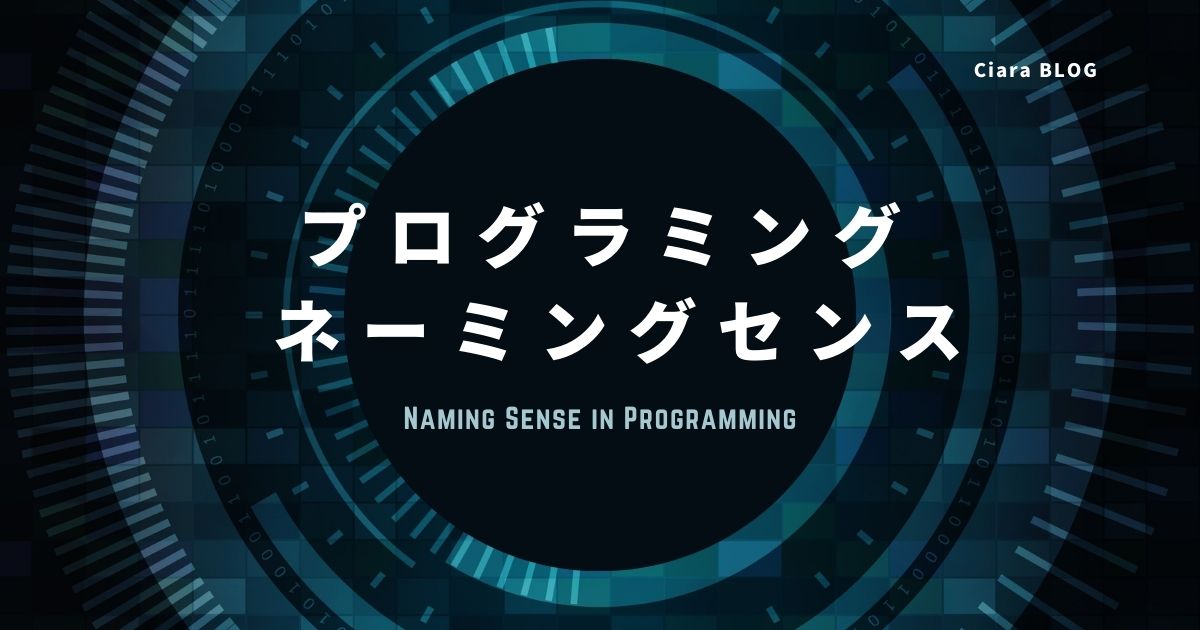こんにちは!社員のWです。
突然ですが、自分自身に「センス」、あると思いますか?
社員Wとしては、この「センス」という言葉、
あ〜ら便利な言葉ですこと!と言いたくなります。
まるで生まれつきの才能のように使われますが、
経験や知見の積み重ねによって磨いていくものだと思うのです。
例えば、ファッションセンス。
例えば、色彩感覚
例えば、選ぶ力。組み合わせる力。
アートやデザインの界隈では特に見かけるような気がしますが、
なにもその世界だけの話ではありません。
エンジニア・プログラマーの皆さんの間にも絶対あると思います。
それはずばり、センスのある変数命名!
私も最近ようやくコーディングに触れる機会が増えた身ですが、
クラス名やID名、ファイル名をつける癖にも個性があるような気がしています。
世の中では命名規則について、ある程度パターン化されています。
今回はこちらを紹介したいと思います!
キャメルケース (camelCase)
概要: 単語の先頭は小文字で、2単語目以降の頭文字を大文字にする。
用途: 変数名・関数名でよく使われる。
パスカルケース (PascalCase)
概要: 単語のすべての頭文字を大文字にする。
用途: クラス名や型名に使用される。
スネークケース (snake_case)
概要: 単語を全て小文字にし、単語間をアンダースコア (_) でつなぐ。
用途: データベースのフィールド名や定数、Pythonの変数名などに使用。
ケバブケース (kebab-case)
概要: 単語を小文字で書き、ハイフン (-) でつなぐ。
用途: URLのパスやCSSのクラス名などで使用される。
定数 (UPPER_SNAKE_CASE)
概要: 全て大文字で書き、単語をアンダースコアで区切る。
用途: 変更されない定数やグローバル変数の定義。
と、こんな感じです!
私が個人的に気をつけているのは、「意味が一見で分かりやすい単語を選ぶこと」「長過ぎないこと」「後々自分だけしか分からない状態にならないこと」を心がけています。
例えば、他の人の開発環境に途中からする時や共同でプログラミングする時にも、
命名規則に気づかず各自が好き放題に命名した結果、
カオス😅🌀な状態になってしまうということが防げそうですね!
プログラマー志望の方は、頭の片隅に置いておくといいかもしれません…!
それでは!